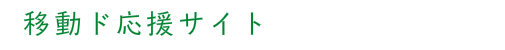「階名」と「音名」とどう違いますか?
「階名」は音の主音に対する相対的な高さを示すもので、それに対し「音名」は音の絶対的な高さを示しています。
「相対的な音程感覚」とはなんですか?
基準となる音を与えられたときに、例えば半音や全音の違いなど、その音からの相対的な音程の幅によって音程を認識していく感覚のことです。
移動ドだと「ド」が移動するのでどこが「ド」なのかすぐにわかりません
調号の一番右の♯が「シ」、一番右のフラットが「ファ」と覚えておくと、すぐに「ド」の位置を見つけることが出来ます。
移動ドで臨時記号がついた時はどう読みますか?
♯は「i」、♭は「e」の母音に変化させます。例えば「ソ(so)」の♯は「シ(si)」、♭は「セ(se)」、「ファ(fa)」の♯は「フィ(fi)」というようになります。「i」のシラブルには上向きの指向性が、「e」のシラブルには下向きの指向性があるためです。このようにあえて異なるシラブルをつけることにより、半音への意識を強く持つことが出来ます。詳しくは、静岡県総合教育センターHP静岡県の授業づくり指針/2中学校における参考事例/資料「ハンドサインと移動ド唱法」をご覧ください。
短調や無調の場合はどうすればよいですか?
短調では、短調の音階の主音を「ラ」と読みます。イ短調では主音のAの音を「ラ」とします。また、無調では一つ一つの音の機能がないため、移動ドを用いる意味はありません。
リコーダーなどの器楽でも移動ドは使える?
リコーダーなどでは、「階名(つまり移動ド)」ではなく「音名」を用います。それぞれの音に対応した鍵盤や運指を覚えるためにドレミを用いるので、移動ドは使用しません。目的に応じた使い分けが必要です。
いわゆる「音痴の人」にも移動ドは有効ですか?
移動ドやハンドサインを用いると、音の高さや、音と音との幅をより意識しやすくなるため、いわゆる音痴(調子外れ)の矯正につながると考えられます。また、移動ドで学習を進めていれば、いわゆる音痴(調子外れ)の子どもの出した音を基準に周りが合わせる、といったことも簡単に出来るようになり、その子どもは、音が合っているという実感を持ちやすくなります。
曲の途中で転調した場合はどうすればよいですか?
変わった調の主音を「ド」と読み替えます。属調転調であればそれまで「ソ」と歌っていた音が「ド」になり、下属調転調であればそれまで「ファ」と歌っていた音が「ド」になります。同じ音高でも、読み方が変わることで転調したことがより意識できるようになります。一方で、一時的な転調であれば、読み替えずに歌う方がスムーズです。
子どもたちが楽譜を見ていきなり移動ドで歌えませんがどうすればよいですか?
あらかじめ教員が移動ドを記したものを用意しておくと良いでしょう。また簡単な曲であれば、教師の範唱を真似することでも対応できます。また、階名の導入の前に数字譜を用いるなど、子どもの学習進度や発達段階に応じた工夫も必要です。「移動ドで歌おう」にある歌唱共通教材の楽譜も、ぜひご活用下さい。
低学年の子どもでも移動ドはできますか?
発達段階に合わせて、ペンタトニック(5音音階)などの構成音の少ない簡単なものから入っていけば、問題なく取り組めます。低学年などの早い段階から移動ドに触れておく方が、後から移動ドを扱うより違和感無く取り組むことが出来ると考えます。
移動ドで歌って音程を把握できたのですが、歌詞で歌うと音程がわからなくなります。
授業などであれば、集団を二つに分けて、「移動ドで歌うグループ」と「歌詞で歌うグループ」で同時に歌っていくと、移動ドのグループの正しい音程が聞こえてくるため、歌詞で歌っていても音程を認識しやすくなります。
ハンドサインを覚えるのは大変です。
まずは「ド」や「ソ」など、楽曲によく使われている音などに限定してハンドサインを使ってみましょう。慣れてきたら、徐々にその数を増やしていくと、抵抗無く覚えることが出来ます。
ハンドサインって楽しいですが何か意味はありますか?
相対的な音程感覚を磨くためには、頭の中で音を思い浮かべることができる能力(内的聴感)を身に付ける必要があります。歌う際にハンドサインを使うことで、自らの音程感覚と視覚による情報を結び付けることができ、子どもたちは内的聴感を実感していくことが出来ます。詳しくは、静岡県総合教育センターHP静岡県の授業づくり指針/2中学校における参考事例/資料「ハンドサインと移動ド唱法」をご覧ください。
「ファ」のハンドサインに子どもが異常に反応します。
コダーイの提唱したハンドサイン以外にも、トニック・ソルファ法で用いられている、人差し指を斜め下に向ける方法もあります。